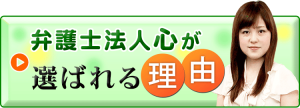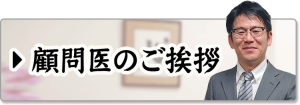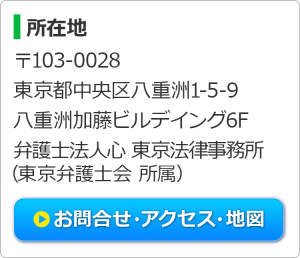茨城県の交通事故裁判例
平成29年3月14日水戸地方裁判所判決
【事案の概要】
交通事故後により腰椎椎間板症が発症したとされ,その治療のために腰椎後方椎体間固定術を受けた原告(事故被害者)について,上記症状は交通事故と相当因果関係があるものであるか争いになった事案。
被告(加害者)は,原告は事故前は肉体労働に従事しており,腰椎椎間板症はこれが原因で発症した可能性が高いと主張した。
原告は,事故前に具体的な腰の症状は発症しておらず,事故が原因であると主張した。
【裁判所の判断】
腰椎椎間板症の発症の原因について,事故前からの生じていた腰椎の変形と,本件事故による衝撃のいずれかもが寄与して発症したと判断し,その寄与度は5割ずつであると判断し,被告は原告に生じた損害の5割分を賠償する責任を負うと判断した。
【判決(抜粋)】
・・・以上によれば,原告には手術による治療をすることが相当な腰椎椎間板症があったと認められるが,交通事故による外傷で腰椎椎間板症が生ずることは限定的なものであるところ,本件事故直後の原告の所見によれば本件事故が原告の腰椎椎間板症の主たる原因であったとはいえず,本件事故のみによって原告に上記の腰椎椎間板症が生じたものとは認められない(原告は,本件事故当日に入院をしなかったのは,搬送されたd整形外科がだったためである旨の主張をするが,そのような事情があったとしても,原告が現実に本件事故当日に入院をしなかったことからすれば,他の病院に紹介するなどして当日入院をするまでの必要はなかったものと認められる。)。
一方で,原告には腰椎椎間板症が発生しているところ,本件事故後原告に椎間板変性の進行や終板変化の進行があったことがうかがわれないこと,受傷後にこのような変化が見られないとすると,その発症には,受傷前に腰椎椎間板に疾病と評価することができる程度の劣化がある可能性が高いこと,20歳代前半の者でも腰椎椎間板に疾病と評価することができる程度の劣化を負うことがあり得ることを考慮すると,原告には,本件事故による受傷前から加齢性変化による腰椎椎間板の変性があり,これは疾病と評価することができるものであったと考えられる。
そうすると,原告の本件事故後の腰椎椎間板の症状は,本件事故前に生じていた加齢性変化による腰椎椎間板の変性と本件事故による衝撃とがいずれも寄与していたと認められる。したがって,原告の本件事故後の腰椎椎間板の症状は,本件事故とも相当因果関係があるものと認められるが,これには本件事故前に生じていた腰椎椎間板の変性も寄与していたものであるから,損害賠償額の算定に当たっては,そのことを減額事由として考慮すべきである
(中略)
前記認定のとおり,原告の本件事故後の腰椎椎間板症には,本件事故前に生じていた椎間板の変性も寄与しているものと認められる。そして,原告は本件事故当時22歳で,火力発電所で肉体労働に従事しており,本件事故の発生前に原告に腰椎に関して痛み等の具体的な症状があったことはうかがわれないこと,鑑定の結果を踏まえて検討したとおり,本件事故が原告の腰椎椎間板症の主たる原因であったとはいえないことを考慮すれば,本件事故前に原告に生じていた腰椎椎間板の変性と,本件事故による影響とのいずれかが原告の腰椎椎間板症の主たる原因であると認めることは困難であるから,それぞれの寄与度を5割と認めるのが相当である。
【弁護士のコメント】
この被害者は,腰のMRIの画像上,腰椎椎間板の変性所見がありました。
腰椎椎間板の変性は,医学的にはよほどの衝撃がない限りは一度の事故で変性が生じることは稀であるとされており,加害者側はこの点を医療鑑定の結果等を証拠として主張した結果,腰椎椎間板の変性自体は事故前からあったものだと判断されました。
一方,被害者は事故当時22歳とまだ若く,具体的な腰の症状も発症していなかったことから,事故前からの腰の変性プラス事故による衝撃も加わった結果,手術が必要なほどの腰椎椎間板症が発症したと判断されました。
事故と事故以外の2つの原因で症状が発生した場合,加害者は,症状に対する事故による影響の度合い(寄与度)に応じて賠償責任を負います。
今回のケースでは,証拠上どちらが腰椎椎間板症の主たる原因なのか断定できなかったため,事故前からの腰の変性が5割,事故による影響が5割と判断され,加害者は損害の50%について賠償する責任を負うこととなりました。
平成25年5月17日水戸地方裁判所判決
【事案の概要】
原告(被害者)は,本件事故によりCRPS(複合性局所疼痛症候群)が発症したとの診断を受けた。
この症状に対して,自賠責保険の後遺障害等級認定では14級にとどまると判断されたが,適切な後遺障害等級は5級相当であると主張して裁判所の判断を求めた。
【裁判所の判断】
原告の症状はCRPSに該当するかについて,裁判所の判断基準を示したうえで,被害者はその要件を満たさないとして,その請求を棄却した。
【判決(抜粋)】
(1)労働者災害補償保険及び自賠責保険におけるCRPSの具体的な認定基準は,〔1〕関節拘縮,〔2〕骨萎縮,〔3〕皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合と定められている(弁論の全趣旨)。
原告の逸失利益,後遺障害慰謝料を認定する上で,原告にCRPSが認められるかどうか判断する場合にも,客観的な認定基準によるべきであり,上記の3要件を充足することが必要であると解するのが相当である。
(2)原告は,CRPS(複合性局所疼痛症候群)と診断されていると主張して,担当医師の診断書を提出する。
同診断書には,今までの経過及び左肩・肘・手関節・手指の著名な拘縮を認め,レントゲンでも前腕から手指にかけての骨萎縮を認めることによりCRPSと考えると記載されている。
しかしながら,原告は,上記の3要件のうち,骨萎縮,皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)が原告に認められることを明らかにする具体的な立証を何らしていない。
そうすると,原告においては,上記の3要件のうち,少なくとも,骨萎縮,皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)が認められないから,原告がCRPSに罹患しているとはいえない。
【弁護士のコメント】
1 レントゲンやMRIの画像上に明らかな異常はなく,外傷は大きくないのに,不釣り合いな強い痛みが残存するという症例があります。
このような症状に対して,複合性局所疼痛症候群(CRPS)と診断されることがあります。
2 CRPSであると認められれば,単なる疼痛よりも高い後遺障害等級が認められる可能性があるのですが,CRPSは原因が良く解明されていない症状です。
そのため,自賠責保険の調査機関は,医師が診断名を付ければ直ちにCRPSであるとは判断しておらず,自賠責保険が採用する認定基準に基づいて,後遺障害等級の認定を行います。
今回のケースでは,自賠責保険の基準上はCRPSではないと判断されたため,被害者は裁判所に判断を求めて提訴しました。
3 CRPSの判断基準については,学説ではいくつかの基準が提唱されています。
しかし,裁判所は自賠責保険が採用する認定基準と同様の基準で判断するとしたため,認定結果は変わらないという判断が下りました。
裁判所は,自賠責保険の判断を尊重(追従)する傾向があり,本件も特に深い理由を示すことなく自賠責保険と同様の基準で判断しています。
平成23年2月7日水戸地方裁判所判決
【事案の概要】
青信号の横断歩道を自転車で横断していた被害者が,青信号で右折した自動車と衝突して死亡した交通事故。過失割合が争点となった。
【裁判所の判断】
被害者には過失がなく,加害者の全面的な過失と判断した。
【判決(抜粋)】
1 争点(1)(事故態様,過失相殺)について
(1)争いがない事実等,証拠(略)によれば,以下の事実が認められる。
ア 本件事故の日時,場所,態様,結果は上記第二,2(1)記載のとおりである。
イ 被告が進行してきた本件交差点手前の道路(県道γ線。片側2車線。以下「本件道路」という。)の最高速度は時速50キロメートルに制限され,両側には歩道が設置され,自転車通行は可となっている。
被告が本件交差点を右折した後に進行する予定であったβ方面の交差道路は幅員が約4.7メートルで,速度の規制はなく,道路中央線や歩道はない。
本件交差点の各出入口には計4箇所の横断歩道が設置されており,本件事故現場はその中の横断歩道の1つ(長さは4.7メートルより少々長く,幅は約3.8メートル)である。
国道α号方面からδ市方面に向かい本件交差点の手前まで,本件道路は緩い左カーブとなっているが,本件交差点付近からδ市方面は直線道路となり,前方の見通しは良い状態であり,本件交差点は,本件事故当時,道路照明により明るい状態であった。
本件横断歩道の手前の歩道(Dは同歩道を進行してきた。)と車道の境付近には植物の植え込みが存在するが,それは地上60センチメートルほどの高さであり,同植え込みが存在することにより被告が視界を遮られD,被害車の発見が遅れたような事情はない。
被告は,本件交差点を国道α号方面からβ方面へ右折進行するに際し,本件交差点の右折方向出口には本件横断歩道が設けられていたのであるから,前方左右を注視し,本件横断歩道上の歩行者等の有無に留意して,その安全を確認しながら進行すべき注意義務があるのにこれを怠り,対向直進車に気を取られ,本件横断歩道上の歩行者等の有無に留意せず,漫然と時速約30キロメートルの速度で右折進行し,本件横断歩道を自転車で横断中のDを右前方約4.8メートルの地点に認め,急制動の措置を講じたが間に合わず,加害車の右前部を被害車に衝突させ,Dを衝突地点(同横断歩道の中央よりやや手前の地点付近)から加害車の進行方向前方約7.3メートルの地点に転倒させ,外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ,同人は意識不明の重体となり,その後同傷害によるびまん性脳損傷等により死亡するに至った。
Dの乗車していた被害車は衝突により飛ばされ,加害車との衝突地点から進路前方やや左約9.2メートルの地点まで移動した。
(2)以上の事実に基づくと,本件事故は被告の一方的な過失に基づくもので,Dには過失が認められない。
被告は,両車の衝突箇所について,被害車の前かご左側に加害車が衝突したと考えるべきであると主張する(上記第二,3(1)ウ)が,衝突地点とDが衝突後転倒した地点及び被害車が移動した地点との場所的な関係,被害車の損傷状況等を総合すると,被告の同主張は採用できない。
さらに,被告は,本件事故は信号機により交通整理の行われている本件交差点で右折中の加害車と同一方向を進行中の被害車が衝突した事案である,Dは,横断歩道を横断するにあたり,わずかでも左右の安全を確認すれば,既に右折を開始している加害車の存在を認識し,停止,減速などの措置をとることにより衝突を回避することは容易であった,ところが,Dは,左方の安全確認を行っていなかったなどと主張する(上記第二,3(1)ア)。
しかし,被告は対向直進車が来る前に右折しようと,本件交差点で一時停止,徐行することなく,時速約30キロメートルの速度で本件交差点を右折進行しようとしたことは上記認定のとおりであり,本件事故の衝突地点・態様,本件事故の際の加害車の上記速度,Dが運転していた被害車の予想される速度などを総合すると,Dが本件横断歩道に進入した際には,加害車が既に右折を開始していたとは認められない。
そして,道路交通法で横断歩道上の歩行者は絶対的に保護されていること(同法38条)に照らしても,Dに過失は認められない。
【弁護士のコメント】
交通事故の過失割合は,過去の裁判例に基づいて一定の目安表のようなものが作成されており,裁判官含め実務家に大きな影響を与えています。
そして,本件のような双方青信号で横断歩道を渡る自転車と右左折した自動車が衝突したケースでは,基本過失割合は10:90が目安とされています。
しかし,上記の割合は絶対的なものではありません。
本件でも,事故現場の状況や自動車側が徐行していなかったことなどを考慮事情として,加害者の一方的な過失を認定しています。